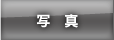HOME�������̑�l�̏�� �F �v���Y�}
�����̑�l�̏�� �F �v���Y�}
�g�\���̋N����₤�h�v���Y�}�����w
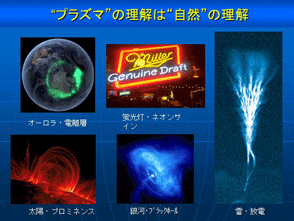 �v���Y�}��Ԃ́A���́A�������̐g�̉���A���R�E�ɐ��������邱�Ƃ��ł��܂��B
�v���Y�}��Ԃ́A���́A�������̐g�̉���A���R�E�ɐ��������邱�Ƃ��ł��܂��B�u������l�I���T�C���̒��ɂ̓v���Y�}�������Ă��܂����A�u���ł����A������C���v���Y�}���������̂ł���A�I�[�������v���Y�}�ł��B
�܂��A���z�\�ʂɔ�������v���~�l���X��A�R���i�A����ɋ�͌n����`�������F����Ԃ�u���b�N�z�[���ߖT������Ƒ��ݍ�p����v���Y�}���d�v�Ȗ������ʂ����ƍl�����Ă���A�n��ł͂��܂�ӎ�����܂��A�F���̎��ɂX�X�����v���Y�}��Ԃɂ���܂��B
�v���Y�}�́A�n��̏����ȃX�P�[������F���K�͂̑傫�ȃX�P�[���܂ŗl�X�Ȏ��R�̑��`�Ԃ�\���`���ɐ[���֗^���Ă��܂��B
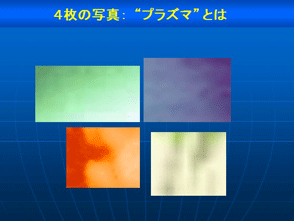
�����Ɏl���̎ʐ^�������܂��B
�����{���b�Ƃ��Ă��ĉ��̎ʐ^�ł����A���ꂼ��́A������̂̈ꕔ���g�債�����̂ł��B
����炪�����z�������ł��傤���B
����ł͂��̈ꖇ�ꖇ�����Ă����܂��傤�B
�ŏ��̓I�[�����̈ꕔ���g�債�����́A��Ԗڂ͑��z�t���A�[�̈ꕔ���g�債�����́A�O�Ԗڂ�"�g�J�}�N"�ƌĂ��j�Z�����u�ō��ꂽ�v���Y�}�ŁA�����A����ǂƌĂ���Ԃ��g�債�����́A�l�Ԗڂ͗��_����d���w�Ɍ������ċ삯�オ���Ȃ̈ꕔ���g�債�����̂ŁA�����͂�������v���Y�}���{���I�Ȗ������ʂ������ۂł��B
�����̐}����ȉ��̓�̏d�v�Ȃ��Ƃ�������܂��B
��́A�����ŋ�������͕K�������܂����̕����ߒ����𖾂���Ă��Ȃ��ۑ�ł���A�e�X�̕���Ő��͓I�Ɍ��������i�W���Ă��镪��ł���_�ł��B
�Ⴆ�A��ȂȂǂ͒��������̗��j�ɂ��ւ�炸�A�Ȃ����̂悤�Ȍ`�ɂȂ�̂��A���̑S�e�͖��炩�ɂȂ��Ă��܂���B
��ڂ́A�v���Y�}�����肳�ꂽ"����ꕔ��"����������ƑS�̓I�Ƀ{���b�Ƃ�����藯�߂̂Ȃ���Ԃ̂悤�Ɍ����܂����A����������čL������ɗ�����"�S��"��c������A�������������ʂȍ\���������Ă���_�ł��B
���ɃI�[�����Ȃǂ͌|�p�̗̈�ɓ���܂����A���z�t���A�[���ȂȂǂ͎��R�̃_�C�i�j�Y�������������Ă���܂��B
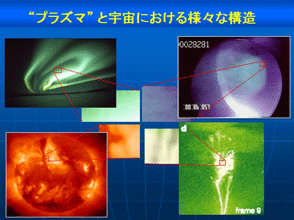
���́u�v���Y�}�v���n�o����l�X�ȕ������ۂ̒T���́A������̃G�l���M�[���Ƃ��Ċ��҂���Ă���j�Z��������A�v���Y�}���[���֗^����F����V�̕��������A����ɂ͕��L�������Ȋw�⍂�G�l���M�[���x�Ȋw�̐i�W�ɏd�v�Ȗ������ʂ����܂��B
���̂悤�ȍŐ�[�̉Ȋw������J�邽�߁A���v���_��J�I�X���_�A�������_�����`���_�A�v���Y�}�̃}�N���ȉ^�����������̗͊w��~�N���Ȍ��q�E���q�ߒ����������q�����w�A���G�ȃv���Y�}�̗��q�^����[�U�[�ɑ�\�������ʎq�ƕ����Ƃ̑��ݍ�p���L�q����Ő�[�̃V�~�����[�V������@����g���邱�Ƃɂ��A�j�Z���v���Y�}�⑊�Θ_�v���Y�}�A�F���E�V�̃v���Y�}�𒆐S�ɁA�Y�Ɖ��p������ɓ��ꂽ�v���Y�}�Ɋւ�镝�L�������w�̗��_�����Ɏ��g�݂܂��B

�����̑�l�̏�ԁEF�v���Y�}
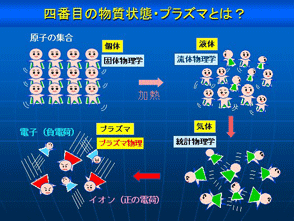
���ׂĂ̕����́A���q����Ȃ��Ă��܂��B�g�߂ȗ�Ő�(H2O)�̏ꍇ�A�ő̂ł���X�����M����ƁA�X���\�����錴�q�̉^��������ɑ傫���Ȃ�A�₪�ĉt�́i���j�ɕω����܂��B
����ɉ��x���グ�邱�ƂŐ��́A�C�́i�����C�j�ƂȂ��āA�����͂��̑��`�Ԃ�ω������Ă����܂��B
���������ɉ��M������A�����d���∳�͂������邱�ƂŁA���Ƃ��ƒ����ł��������q�̓v���X�d�ׂ̃C�I���ƁA�}�C�i�X�d�ׂ̓d�q�ɕ������܂��B
���̂悤�ȁA�����̃C�I���Ɠd�q�����݂��A�e�X���ꌩ�Ɨ��ɁA�����ʼn^�����Ă����Ԃ��u�v���Y�}�v�ł��B
���̃v���Y�}�́A�C�I���Ɠd�q���قړ�������A�S�̂Ƃ��Ă͒������ۂ���Ă��邽�߈ꌩ���ʂ̉t�̂�C�̂̂悤�Ɍ����܂����A���ꂾ���ł͋L�q�ł��Ȃ��u�V���Ȗ@���v������邱�ƂɂȂ�܂��B
���ꂪ�u�����̑�l�̏�ԁv�ƌĂ�闝�R�ł��B
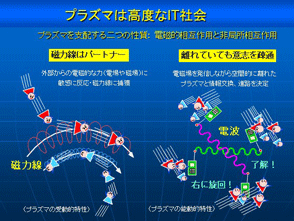
���̖@���́A�v���Y�}�̊e�C�I�������͐��ɑ��Ă点���Ɋ������^���̂��Ƃ��w���܂��B
�܂�A�u����v�Ɓu�v���Y�}�v�̓p�[�g�i�[�̊W�ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B
�܂��A�v���Y�}���g���F�X�Ȏ�ނ̓d��⎥��A���Ȃ킿�d���g���M���Ȃ���A�������ċ�ԓI�ɉ������ꂽ�v���Y�}�Ƃ���Ɍ�M���s���A�����������Ȃ��玩�g�̐i�H�����߂�Ƃ��������������܂��B
���ꂪ��S�Ԗڂ̖L�x�Ȍ��ۂ�n�o����N���ɂȂ�܂��B
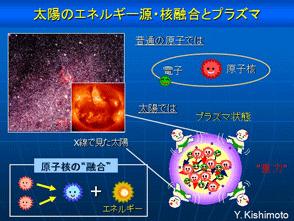
����ł́A�j�Z���Ƃ͂ǂ�������ԂŋN����̂ł��傤���H
�j�Z�����ۂ��N�����Ă�������Ƃ���\�I�Ȃ��̂͑��z�ł��B�v���Y�}�̒��Ō��q�j���m�������ŏՓ˂���Ɗj�Z���������N�����A���d�����q�j�ɕς��܂��B
���̍ہA�傫�ȃG�l���M�[�����o����܂����A���ꂪ���z�G�l���M�[�̋N���E�j�Z���ł��B
�v���Y�}�́A���͂��������߉����Ȃ���A��U���Ă��܂��܂��B�������A���z�͒n����30���{�̎��ʂ������Ă��邱�Ƃ���A�傫�ȏd�͂��������A�v���Y�}�������E�����Œ����Ԉ���Ɉێ�����܂��B

���z�̎�v�ȕ������f�ł���A���x��1,500���x���x�ł����A���x��1cc������200g�ƌő̐��f��2000�{�A���̂Ƃ��̈��͂�240Gbar�ɒB���܂��B
���R���̗̈悩����o�����S�G�l���M�[�͓V���w�I�ʁi3.85�~1026W�j�ł��B
�������A�����1m3������Ɋ��Z�����100W���x�Ől�Ԃ����M����bio-chemical�ȃG�l���M�[��70kW���x�ł��邱�Ƃ��l����ƈӊO�ɏ������Ƃ������Ƃ��킩��܂��B
����́A���f���x�[�X�ɂ������萔�����\���N�̔��ɂ������Ƃ��������ł��邱�Ƃɂ��܂����A�n��ŎY�Ƃ��x����G�l���M�[���Ƃ���ɂ́A�������Ă��P�ʗ������[�g�������萔MW�Ƒ��z�Ɣ�ׂ�ƌ��Ⴂ�Ɍ����I�ȃV�X�e�������K�v������A���ꂩ�猩�Ă��j�Z���͕K�������e�Ղł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��킩��܂��B

�v���Y�}�E�j�Z�������ւ̃A�v���[�`
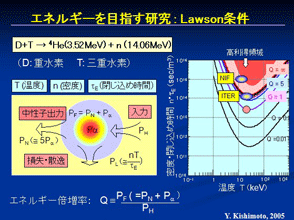
�n��̊j�Z���ł����A�j�Z�������f�ʐς̍ł��L���Ȕ����A���Ȃ킿�d���f�ƎO�d���f���x�[�X�ɂ��܂����A�����I�ɂ́ADD������DHe3���̒����q�t���[�̔���������ɓ���邱�Ƃ��K�v�ł���A���̂悤�Ȑ�i�I�ȔR�����g������������w�𒆐S�ɐ��͓I�ɂȂ���Ă��܂��B
��}�̓��[�\���}�ƌĂ��j�Z�����G�l���M�[���Ƃ��Đ�������������������Ă���A�v���Y�}�̉��x�Ɩ��x�A���ꂩ�炻����ێ���������ߎ��Ԃ̑㐔�W���ŕ\����܂��B
�O�����瓊������G�l���M�[�Ɗj�Z���o�͂̔�A������G�l���M�[���{���ƌĂсA�Ȍ�Q�Ƃ��Ē�`���܂����A����Q���P�ɂȂ�������Ȋw�Ibreak-even�ł���A��������ł�DD�R����p���������I�Ȋ��Z�l�ł͓��{���q�͋@�\��JT-60�ł��łɒB������Ă��܂��B
ITER��NIF�ł͎��ۂ̊j�Z���R���ł���d���f�ƎO�d���f��p���āA��荂Q�̒l���A����ɂ͊O�����̓[���ł��������ێ��ł���Q��������̊j�Z���_��ڎw�����ƂɂȂ�܂��B
��������Ɗ�������
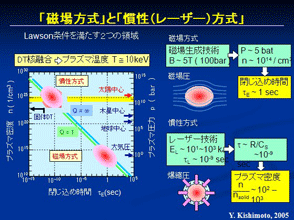
�j�Z������������ɂ́A��̕��@�A�u��������v�Ɓu�����i���[�U�[�j�����v������܂��B
���}�ł�DT�j�Z����O���ɁA�v���Y�}���x��10keV�ɌŒ肵�A�����ߎ��ԂƖ��x�̕��ʂŌ݂��̊W�������Ă��܂��B
���[�\�������Ɋ�Â��āA�j�Z�����{��Q���P�y��Q��������̃��C����������Ă��܂��B
�v���Y�}�̖��x�ƕ����ߎ��Ԃ݂͌��Ƀg���[�h�I�t�̊W�ɂ���A�u��������v�ł͒ᖧ�x�Œ��������ߎ��ԁA�u���[�U�[�����v�ł͍����x�ŒZ�������ߎ��Ԃ̗̈�Ɉʒu���܂��B
���̗̈�̌���̎d���́A�u��������v�̏ꍇ�́A���ꈳ�Ńv���Y�}������߂邱�Ƃ��玥��̐����Z�p��������߂���v���Y�}���͂����܂�A���ꈳ�ɑ���v���Y�}�����T���i�x�[�^�l�ƌĂ�܂��j�Ɖ��肷��ƁA���x��1cc������1014�����v������܂��B
���Ƃ̓��[�\���������琔�b�̕����ߎ��Ԃ����܂�A���̕����ߎ��Ԃ������I�ɒB���ł��邩����������̐��ۂ����߂邱�ƂɂȂ�܂��B
����A�u���[�U�[�����v�̏ꍇ�̓��[�U�[�̔��k�����g�����Ƃ���A���[�U�[�̔����Z�p�����ƂȂ�A���\kJ���琔�SkJ�̃G�l���M�[���i�m�b�̃p���X�ɏW��������e�N�m���W�[���w�i�ƂȂ�܂��B
�����ߎ��Ԃ͔R���������ŗ��܂��Ă��鎞�ԁi�������ԁj�Ō��܂�A���̊������Ԃ����[�U�[�p���X���̃i�m�b���x�ƍl����ƁA���Ƃ͎�������Ɠ��l�Ƀ��[�\���������獂���x�A���Ȃ킿�ő̖��x�̐�{���x���v������邱�ƂɂȂ�܂��B
�Q�l�̂��߉E�̎��Ɉ��͂������Ă��܂����A����ł͐��o�[���Ƒ�C�����x���ł����A���[�U�[�����ł͐��S�f�o�[���ƁA���z�̒��S�ɕC�G���鈳�͂ɂȂ�܂��B ���҂̃X�P�[���̈Ⴂ��1010�ȏ゠��܂����A���̂悤�ɑ傫���u�������p�����[�^�̈悪���[�\�������Ƃ����ȒP�ȑ㐔���Ō��т����Ă���̂͋����[���_�ł��B
��������̎�ށF�u�g�[���X�n�v�Ɓu�J���[�n�i�~���[�^�j�v�@����с@�u�g�J�}�N�n�v�Ɓu�w���J���n�v
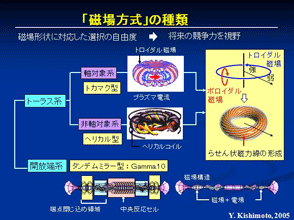
��������ɂ��j�Z���ł́A�p���鎥��`��ɑ��Ċ���̑I���̎��R�x������A�����̍��������͂�����ɓ���Čn���I�Ɍ������i�߂��Ă��܂��B
�����͑�܂��ɓ�ɕ��ނ���A��̓h�[�i�c��ɂ��Ē�������̒[�_���g�|���W�[�I�ɂȂ�����u�g�[���X�n�v�ƁA�����I�Ȋȑf���͕ێ������܂ܒ[�_�ɗl�X�ȍH�v���{���ăv���Y�}������߂�u�J���[�n�v������܂��B
�J���[�n�͌��݁A�}�g��w�̃^���f���~���[�^�ƌĂ��Gamma10�E�ES�Ɍ������i�߂�ꂨ��A��̒[�_�ɂ����āA����\�������ł͂Ȃ��A���͐��ɉ����������Ɂu�d��v��\���I�ɔ��������邱�Ƃɂ���ăv���Y�}������߂錤�����i�W���Ă��܂��B
����A�g�[���X�n�́A���͐���P���ɘA�����������ł͓����ƊO���Ŏ���ɋ��オ����A���ꂪ�����ƂȂ��ēd�ꂪ�������A�v���Y�}��ێ����邱�Ƃ��ł��܂���B
���̓d���ł��������߂ɂ̓|���C�_�������ɂ����ꐬ�����������ē����ƊO����A��������K�v������A���̂���"�点���"�̎���\������邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�܂��B
���̂点��������������@�Ƃ��́A�v���Y�}���g�ɓd���𗬂����ꂪ���|���C�_�������p����g�J�}�N�����ƁA�w���J���R�C���ɂ���ĊO�����璼��"�点���"�̎�������w���J������������܂��B
��҂̃w���J���n�͓d�����ӎ����ė����K�v���Ȃ����ߒ�퐫�������ӎ��������̂ƌ����܂��B
���̂Ƃ��A�g�J�}�N�ł̓g�[���X�����ɂ̓v���Y�}�͈�l�őΏ̐������邱�Ƃ���u���Ώ̌n�v�Ƃ�сA�w���J���^�̓w���J���R�C���̍�鎥�ꋭ�x���g�[���X�����ɕω����đΏ̐����Ȃ����߁u�Ώ̌n�v�ƌĂт܂��B
�����݂͌��ɑ���I�ł���A���ꂼ��"�Ώ̐�"�̂��镨����"�Ώ̐�"���Ȃ��������Ή����Ă��܂��B
�Ώ̐��̗L���Ɋւ��ẮA�f���q���_���͂��߁A�����̕����������ł���悤�ɁA���ꂼ��ɋ����[�������ߒ������݂��܂��B
�g�J�}�N�n�ƃw���J���n�́A���ꂼ��Ɉ꒷��Z������܂����A�ۑ�̍����Ɍ����Č������i�߂��Ă��܂��B
����j�Z�����u�F�i�s�U�O�i�g�J�}�N�n�j�Ƃk�g�c�i�w���J���n�j
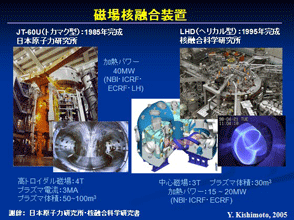
�����͂��ꂼ��A���{���\�����^�̃g�J�}�N���uJT-60�i���{���q�͊J���@�\�F�߉ό������j�Ƒ�^�w���J�����uLHD�i�j�Z���Ȋw�������j�̊T�ςƐ^��e��������Ă��܂��B
�g�J�}�N�͑Ώ̐��̂���h�[�i�c�`��ł����A�w���J���͐^��e����A�����v���Y�}���R�����I�ȃw���J���`��ɂȂ��Ă��܂��B
LHD�́A��^�̃w���J�����u�ł͐��E�ŏ��߂Ă̒��`�����u�ŁA�R�C���͉t�̃w���E���ŗ�p����A�^��e����u�ĂĈꉭ�x�߂��v���Y�}�Ƌ������܂��B
�^��e����ӂɂ̓v���Y�}�����M������d�����쓮�����肷��l�X��RF���u�◱�q�r�[�����ˑ��u�����t�����Ă��܂��B
���������i���[�U�[�j�Z���j�̎��
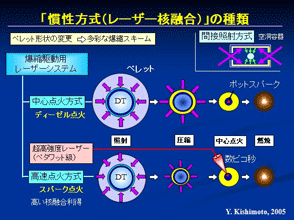
���������̓��[�U�[�j�Z���ɑ�\����܂����A���k���쓮���郌�[�U�[�V�X�e���Ɗj�Z�����N�����R���y���b�g���Z�b�g�����`�F���o�[�͕������Ă��邽�߁A�y���b�g�`���ύX���邱�Ƃő��ʂȔ��k�X�L�[����I���ł���Ƃ������ݓI�ȃ����b�g������܂��B
��@�Ƃ��ẮA�u���S�_�Ε����v�ƌĂ����̂ƁA�ߔN���ڂ��W�߁A����w�����S�ɐi�߂Ă���u�����_�Ε����v�ƌĂ����̂�����܂��B
���̒��S�_�Ε����E�����_�Ε����͂Ƃ��ɁA�����̃��[�U�[�r�[�����l����������Ȃ�ׂ��ψ�ɏƎ˂��A�y���b�g�\�ʂ������ɂ��ă��P�b�g���˂Ɠ��l�̃v���Y�}�̕��o�E�A�u���[�V�������N�������A���̔���p��DT�R����������Ɉ��k���܂��B
�����܂ł͗��҂̊T�O�͂قړ����ł����A���S�_�Ε����ł́A�����ɖȖ��ȃy���b�g�f�U�C�����s���A�ő刳�k�ɒB����O���玩���I�ɔ��k�R�A�̒��S�̈�ō����v���Y�}�i�z�b�g�X�p�[�N�j�����A����̒Ⴂ���x�̔R����_�E�R�Ă�����A�Ƃ����V�i���I�ł��B
�Ƃ��낪�A���̃z�b�g�X�p�[�N������ɂ̓y���b�g���S�ɍ�����Ԃ�ۂ��Ȃ���y���b�g���k���邽�߁A���ʓI�ɑ傫�Ȕ��k�G�l���M�[��K�v�Ƃ��A�܂��ɂ߂Đ��x�̍����f���P�[�g�Ȉ��k���K�v�Ƃ���܂��B
������ɘa�����@�Ƃ��āA��Z�����ō��ꂽ�L���r�e�C�[�Ƀ��[�U�[���Ǝ˂��A��x�A��l���̍���X���ɕϊ����āA������ēx�y���b�g�ɏƎ˂���u�ԐڏƏƎ˕����v�ƌĂ���@������܂��B
����͕č��𒆐S�Ɍ������s���Ă��܂����A�y���b�g�����G�ł��邱�Ƃ�X���ւ̕ϊ��������ɖ�肪�c���Ă��܂��B
�����ɑ���V���ȕ��@���u�����_�v�ƌĂ����̂ł��B
����̓y���b�g�̍ő刳�k���ɍ��킹�ăy�^���b�g�i10**15W�j���̃��[�U�[�𐔃s�R�b�̏u���ɏƎ˂��A����ɂ��z�b�g�X�p�[�N�������I�ɐ��������@�ł��B����j�Z���̌��t�Ō�����"�lj��M"�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
���̃y�^���b�g���[�U�[�ƍ����x�v���Y�}�Ƃ̑��ݍ�p�̓��[�U�[�̃G�l���M�[���x�����ɍ������ߑ��Θ_�̈�ɓ���A���̃v���Z�X�͑������G�ɂȂ�\��������܂����A�Ⴂ���[�U�[�G�l���M�[�ō����j�Z�����������҂ł���Ƃ���Ă��܂��B
���[�U�[�j�Z�����Eu�F����w����XII��
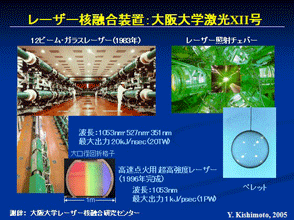
����w���[�U�[�j�Z���Z���^�[�ɂ����ĉғ����Ă��郌�[�U�[�j�Z�����u����12���̑S�i�ƃ��[�U�[�Ǝˏu�Ԃ̃^�[�Q�b�g�`�F���o�[���̗l�q�A����сA�����_�Ηp�̃y�^���b�g���[�U�[�̑S�i�������Ă��܂��B
�g��1�~�N�����̃K���X���[�U�[���AKDP�����ƌĂ��g���ϊ�������ʂ��āA�g��0.5�~�N�����̂Q�{�����g�̃O���[�����A����сA�g��0.33�~�N�����̂R�{�����g�̃u���[���ɕϊ�����A���悻1�i�m�b�̊Ԃ�20KJ�̃G�l���M�[�i20TW�j���j�Z���y���b�g�ɏƎˉ\�Ȑ��E�ő勉�̃��[�U�[���u�ł��B
���{�ɂ�����j�Z�����u�̐i�W
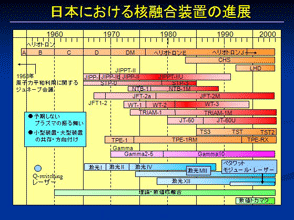
���̐}�͓��{�ɂ�����j�Z�����u�̐��ڂ������Ă��܂��B
�j�Z����1958�N������J�ƂȂ��Ă��܂����A���{�ł͋��s��w�̃w���J�����u�����{�Ǝ��̃A�C�f�B�A�Ƃ��Ă��łɂ��̎�������X�^�[�g���܂����B
���̃v���W�F�N�g�̓w���I�g����E�ɔ��W���A�w���J���n�̊�Ղ�z���Ȃ���A���ꂪCHS�ƂƂ��ɐ��E�L���̒��`����^�w���J�����uLHD�̐v�ɔ��f����Ă��܂��B
�g�J�}�N�̓w���J���Ɏ�x��ăX�^�[�g���Ă��܂����A�v���Y�}�̕����߂���r�I�ǍD�ł��������Ƃ���A���̎������E���ɋ}���ɍL�����Ă��܂��B
���̒�����g�J�}�N�̒��^�]��ڎw�������������łɃX�^�[�g���Ă���A�d���쓮�̊�Ղɑ傫���v���������s��w��WT�V���[�Y��A���d�����u�Ƃ��Đ�w�������B��w��TRIAM�����݂���A��^���u�̌����ɂȂ����Ă��܂��B
�܂��A�J���n���}�g��w�œ������ɃX�^�[�g���Ă���A���[�U�[�j�Z���́AQ���[�h�X�C�b�`����������P�O�N���o�����Čv�悪�X�^�[�g���A����w�̌���12���Ɏp����Ă��܂��B
���̐}����A�j�Z���̔��W�`�Ԃɑ��ē�����I�ȓ_���ǂݎ��܂��B
�ŏ��́A�e�X�̑��u�Ō��ݏ����̔�r�I�Z�����Ԃő����̉��ǂ��{����āA���������v���Y�}���@���ɗ\�����Ȃ����G�ȐU���������������Ƃ����_�ł��B
��Ԗڂ́A���^���u�Ƒ�^���u�͑����̏ꍇ�y�A�ŋ������A���^���u�ʼnȊw��Ղ̃x�N�g�����߂Ȃ����^���u�ł̌����������I���`�������W�O�ɍs���Ă���_�ŁA���̂悤�Ȍ����X�^�C�����j�Z��������Z���Ԃɑ傫���i�W�E����Ă��܂��B
���������ƕ��s���ė��_������X�[�p�[�R���s���[�^�̒��������W��w�i�ɃV�~�����[�V�����������������������������A�ߔN�ł͌v�Z�@�̒��Ƀg�J�}�N���͂��߂Ƃ����j�Z���v���Y�}���Č����鐔�l�g�J�}�N�������̃V�~�����[�V�����Ɋ�b��u�����V���������X�^�C�����萶���Ă��܂��B